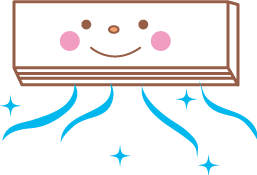高校入試WEB出願で生じた問題について
今年度(2024年度)、群馬県高校入試への出願が突然、すべてWEB出願になりました。全群教はデジタル化による事務効率化について反対ではありませんが、今年度のWEB出願への移行はあまりに拙速な見切り発車(関係職員への説明が10月10日)で、トラブルが続出するのは明白でした。そこで9月に緊急要求を行い、「トラブルに関しては県教委が責任をもって対応する」と約束しました。しかし案の定、中学校の職員の過重労働に拍車をかける結果となりました。
そこで3月5日に再度交渉を申し入れ、3月18日に制度改善について、県教委高校教育課・義務教育課との話し合いを行いました。
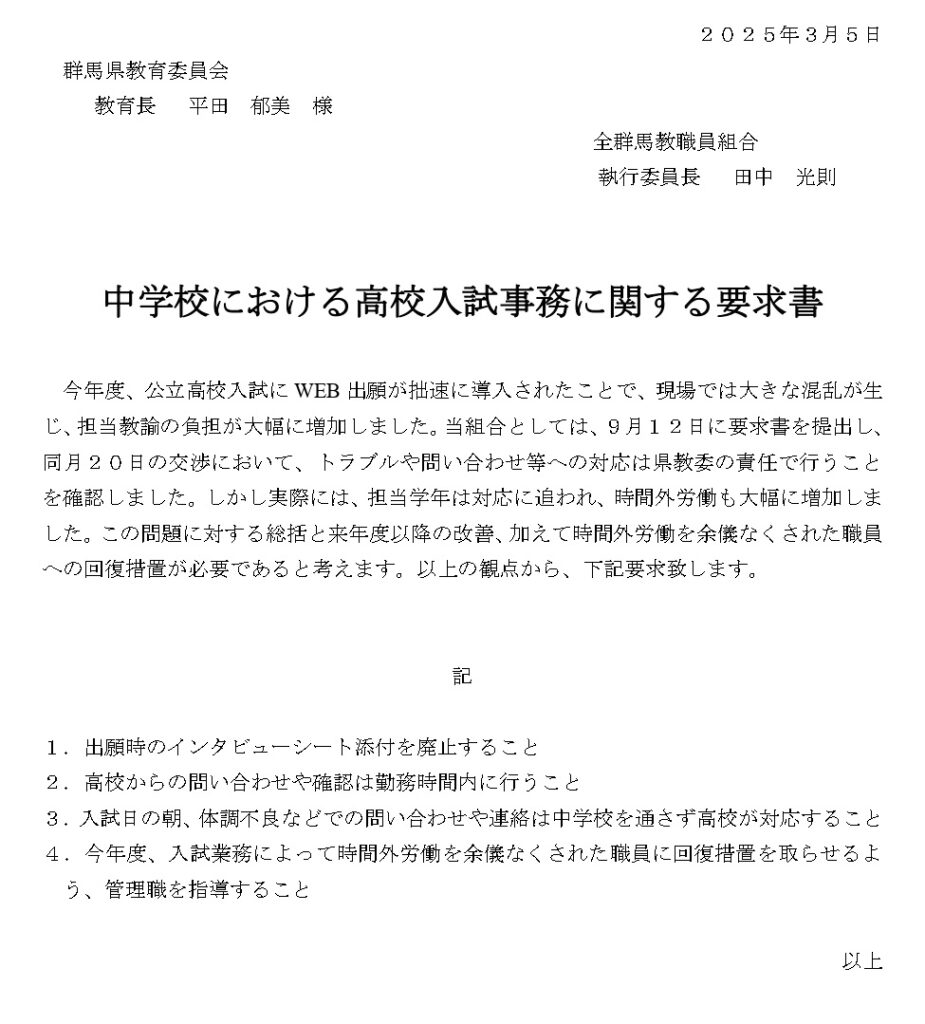
全群教と県教委の意見交換(3月18日)
WEB出願は多くの点で業務の効率化をすすめることにつながることに異論はない。しかし中学校での、実務を含めた進路指導について、その過酷な長時間過密労働の実態を県教委側には十分な理解がない。その改善がなされなければ、ほんとうの意味での業務の効率化、教職員の長時間過密労働の解消にはつながらない。
中学校では、生徒の進路・進学指導だけではなく、保護者などとの電話対応や高校との調整や話し合い、さらに郵送物発送等などの細かい作業などを含めた一切の事務等、進路・進学にかかわることは、授業や各種校務分掌、行事等の準備等、学校を進めながら行っている。当然、その仕事は勤務時間を大幅に超えなければ消化しきれないものである。中学校における進路指導とそこに生じる事務量の認識を具体的に認識されることを強く求める。
G-smartによるWEB出願について、早急に改善すべき点
1.保護者・生徒の作業としてわかりづらく、教職員に過剰な負担を強いる「インタビューシート」は廃止すること。
少なくともG-smartへの添付はやめること。内容の指導にとどまらず、G-smart上に添付するための作業を保護者・生徒にまかせることができず、その対応に勤務時間外、場合によっては夜遅くまで教職員が追われることになった。しかも、その書く内容や書き方等が高校によって違うことも対応を難しくした。また、事前に県教委に確認していたことが、直前になって高校側のHP等で違う内容で指示されるなど事態もあり、中学校に対する不信感や保護者・生徒の不安につながっていた。
高校教育課は、「何か、面接時に話すための材料がないと、うまく喋れない生徒への配慮」と説明しました。理解できなくはないですが、一律に課すことで膨大な事務量の増大を招いていることが問題です。また、学校現場で手を入れ過ぎる傾向があることも問題です。本来、中学の教師が確認すべきは誤字脱字程度のはずですが、ひどい場合は教師の作文のようになっています。この点についての問題認識は、組合と教委は同一です。しかし、そういった現状を生み出しているのは今の仕組みであり、それを継続していけば同じ問題が起こり続けます。そもそも「インタビューシートはそうまでしてやらねばならないものなのか?」という、根本的な議論が必要です。
2.高校への指導を徹底し「外字処理」等を含めた細かく具体的な作業内容について共通理解をはかること。
Web上で起こる様々な課題について事前に県教委に確認していたものを、高校側から「不備」「不適切」のように指摘する連絡があるなど、県教委から高校への指導や確認ができていないと思われる場面があった。こうしたことが起こる度に確認作業や保護者連絡に忙殺され、中学校の教職員には大きな負担となっていることを理解するべきである。
県教委から高校側への指導が行き渡っておらず、中学校側の負担が増えました。保護者は当然、中学校に相談してきます。そして私たちはそれを無下に断ったりしません。なぜなら教師だからです。そもそも見切り発車で始めたこと自体が根本的な問題です。県教委は「大きなトラブルがあったという連絡は受けていない」と言いました。それはそうでしょう。大きなトラブルにならないように、中学校の教員が勤務時間を大幅に超過して対応していたからです。教員の善意と無償労働を前提とした仕組みは絶対に変えなければなりません。
3.勤務時間外の電話連絡やWeb上の発表時間設定は早急に是正すること。
高校への連絡は勤務時間外にはできない場合がほとんどであるのに対し、中学校への問い合わせや連絡は何の問題意識もなく平気で5時過ぎに行われていた。高校には勤務時間があり、中学校には勤務時間はないかのような対応についてその意識改善とともに早急の改善をもとめたい。また志願状況等、Web上での発表が午後5時に設定されていた場合がある。中学校ではその発表によって生徒への指導などを検討しなければならない事が多く、しかも時間がないなかでの作業は、当然のように勤務時間外労働となった。県教委の発表を中学校がどのように把握し生徒の進路指導に活かしているのかなどの実態を義務教育課はしっかり把握し高校教育課は教職員の勤務時間をふまえた時間設定をするべきである。
この点について、県教委は大いに反省をしていました。次年度以降の改善を期待します。
4.要項を含めた高校入試に関わる内容は夏季休業前に決定し発表すること。
全群教の指摘もあり年々日程の発表は早くなっているとはいえ、具体的な内容は遅いのが現状である。今年度は試行・実施開始年であるとしても遅すぎる対応であり中学校ではその対応に苦慮した。次年度以降は少なくとも夏期休業前には要項を含め高校入試の内容を発表し、中学校での準備が始められるようにするべきである。
この点は全群教が毎年指摘し、少しずつですが早くなっており、努力に感謝したいと思います。しかし今年度は、最初の関係者説明会が10月10日と、本当にあり得ない日程でした。入試事務は、絶対にミスをしないように、中学校側は本当に気を遣います。日程を早めることは教職員のためでもありますが、結局は生徒のためです。
5.旅費を含め大幅に減額した高校入試に関わる予算を「進路対策費」として中学校職員に支給すること。
Web出願によって、高校への書類提出等で必要な旅費は大幅に減額している。その予算を長時間過密労働のなかに置かれた中学校教職員に支給する必要がある。中学校の進路にかかわる労働実態を把握するためにも、こうした具体的な「手当」措置が必要である。
中学校の教員は、授業などの日常業務に加えて入試事務を行っています。どれだけ効率化しても勤務時間内には終わりません。であれば、せめて手当を支給するよう要求しました。それも無理なら超過勤務時間に対する配慮が必要です。
6.現場の声に耳を傾けること。
そもそも現場の声を聞くことなく突如WEB出願システムが導入されたことに憤りを感じる。システムの不具合も多く、現場の教職員に新たな進路事務を強要し、多くの生徒・保護者に多大な心配をかけたことに対してお詫びの一言も無いことに対して、現場を軽視している姿勢がうかがえる。年度途中より突如導入されたシステムについて詳細な説明も無かったため、例年通りに調査書データ作成準備に取りかかった。しかし蓋を開けてみれば調査書データは学年別で作成することになり、改めて学年別にデータを分ける作業が発生した。これほどまでに大掛かりな出願システムの変更であるならば、来年度入学する新一年生より新たな形で調査書データを蓄積し、三年後の入試に備える等、周到な準備のもとで始められるべきであった。あまりにも拙速な導入に現場は大変混乱し、新たに発生した進路事務の負担を被ることとなった。
根本的な問題はここにあります。「下の者は上で決めたことをやればいい」とばかりに、現場の教職員に何の相談もなく、一方的に仕事が降りてくることに、私たちは憤っているのです。現場の声をきちんと聞けば、もっと効率のよい方法も出てきますし、何より私たちが納得して仕事ができます。日本の労使関係に決定的に欠けているのは「リスペクト」ではないでしょうか。
7.非効率的な連絡体制を改善すること
WEB出願のことについて問い合わせをする場合は「中学校→地教委→教育事務所→県教委」という流れがあったが、「教育事務所の担当が不在だから、今日は県教委に問い合わせできない」と地教委に質問を跳ね返されたことがあった。「明日保護者会があるので、早急に対応が必要である。県教委に直接聞いていただけないか」「回答を得られるのが遅れれば、不利益を一番に被るのは生徒である」とお願いしても、「できない」の一点張りだった。むしろ、「管理職を通して地教委に問い合わせるように」という、新たなルールを設けられた。
WEB出願に関しては、今年度より導入された仕組みのため、管理職も理解しておらず、地教委の担当者も理解していない状態であった。その流れの中での質問は「伝言ゲーム」となり、質問の意図が正しく伝わらなかった。
また各教育事務所には、WEB出願について話が分かる人は一人しかいないのだろうか。もしもその人が病休等で長期間職場を離れるようなことがあった場合、どうするつもりであったのか。
9月の交渉で「トラブルには県教委が対応する」と合意しており、現場で実際に困っている担当者から県に直接連絡しても問題なかったはずである。つまり、地教委の担当者の「忖度」によって「直接連絡してはいけない」というルールを作ったと考えられる。もちろん、何でもかんでも現場の教員が教委に問い合わせていたらキリがないが、今回はレアケースである。しかも一方的な制度変更で、現場を混乱させたのは教委側である。
労使は「上下」ではなく「対等」の関係
今回、全群教と県教委(高校教育課と義務教育課)で意見交換できたのは、非常によかったと思います。上述したことだけでなく、1時間かけてじっくり対話できました。かなり厳しい意見も伝えましたが、丁寧に対応していただきました。私たちの意見がすべて通るわけではありませんが、全群教が異議を申し立てなければ、拙速な制度変更による現場の負担増は「なかったこと」になっていたところです。
教委は「これから学校に行ったり、アンケートをとったりして検証する」と言いましたが、「みなさんが学校に行っても、いいことしか言われませんよ」と伝えました。学校の労働環境改善が進まない最大の理由は、教職員による校長への忖度、校長による地教委への忖度、地教委による県教委への忖度にあるのだろうと思います。なぜならそこには「上下」の関係があるからです。
使用者と「対等」の立場で話ができるのは組合だけです。なぜなら法律にそう書いてあるからです。おかしいことには「おかしい」と言う組合がなければ、すべては上意下達で自動的に決まっていき、どんどん労働環境は悪化していきます。
今はまだギリギリ頑張れていますが、組合に入る人がどんどん減っていけば、今の活動も維持できなくなってしまいます。逆に「組合に入るのが普通」という状況になれば、職場の風通しがよくなり、労働環境は改善します。私たちは「働きたくない」のであはありません。「納得して働きたい」のです。そしてそれは結局、子どもたちの教育環境の改善へつながります。全群教の活動は、「公教育を守ること」そのものです。
公教育を守るため、一人一人の人権を守るため、「組合に入るのが当たり前」という社会を作っていきたい。