「産育休」権利獲得の歴史

目次
産休制度は戦前からあった?
最初に、教員を対象にした産休制度が導入されたのは1908年の長野県です。何と、戦前に導入しています。しかし、時代の方が追いつけなかったのか、広がることはありませんでした。
※長野県は現在、「1年間の不妊治療休暇(無給)」を認めています。よいものはどんどん真似すべきです。全群教は同様の制度を群馬でも導入するよう求めています。
1911年、工場法に、産休に関する規定を書き込む。
1922年、文部省は、女教員・保母に産前産後の有給休養を認めるよう訓令発出。
明治以降の日本といえば、天皇陛下バンザイ、家父長制バンザイ、パワハラ・セクハラ・モラハラが常識の社会。そんな中で、実効性があったかどうかはともかく、「出産に関する権利」が一定程度認められていた、というのは意外ではないでしょうか?
当時の日本政府は人権意識が高かったのでしょうか?
もちろんそんなはずありません。
1910~20年頃といえば、そう、『大正デモクラシー』です。民衆が自ら権利を求め、戦ったからこそ、一定の権利を勝ち取ることができたのです。口を開けて待っていても、権利が空から降ってくることはありません。
大正時代、一時的に民主化運動が盛り上がりますが、昭和恐慌以降はファシズム国家化が進み、15年戦争(満州事変~太平洋戦争)に突き進みます。産休どころか、「欲しがりません勝つまでは」「産めよ殖やせよ国のため」という時代の到来です。
産休代替法の成立
戦後、日本国憲法に男女平等が規定されましたが、長年かけて培った『差別意識』は簡単に消え去るものではありません。当時の日教組の中でも、男性組合員による女性蔑視の意見が多くあったようです。
ちなみに1989年、日教組(日本教職員組合)が労使協調型の日本労働組合総連合会(連合)に加盟することに反対し、日教組を離脱した人たちが1991年に結成したのが全教(全日本教職員組合)です。それまでは1つの組合でした。全群教(1989年結成)は、全教に加盟しています。
・男女の同一賃金は不当
日教組教育研究集会の記録から作成 木村松子氏の論文(2002)より
・女は男よりも能力その他の点で下である
・女教師は45歳を過ぎた人に退職勧告
・婦人教員の高齢高給者には圧力
・子持ちの教員や共稼ぎの教員は整理の対象
労働基準法で産休は認められましたが、産休代替制度がなかったため、産休を取ると同僚の負担が増えます。「(産休を取る)女性教員が、男性と同じ給与をもらっているのはおかしい」という主張が、組合の中でもなされていました。
初代日教組婦人部長だった高田なほ子は、産休代替法実現のため社会党から出馬し、参議院議員となります。高田は、校長の要請によって出産当日まで教壇に立ち、命の危険を感じた自身の経験に根差して、「産休代替法」の制定に意欲を燃やします。
ちなみに、全教は(もちろん全群教も)特定政党を支持することはありません。組合員に支持を押し付けることもありません。どの政党の議員にも組合としての要求を投げかけ、一致できる点で協力します。
1955年、高田らは日教組案をもとにした産休代替法案を提出。すると与党から別の「産休代替法案」が提出され、与党案を軸とした法律が成立しました。不十分な内容ではあったものの、与党も運動の高まりを無視できず、法制化せざるを得なかったのです。
しかし法律は制定されたものの、実際には代替教員が配置されず、産休が取れない事例が続出します。そこで日教組婦人部は、産休代替教員が配置されることを目標として運動を展開します。そして粘り強い交渉によって1961年、産休代替法が改正され、産休代替教員の配置が義務化されました。
母親との連帯
日教組は教育研究集会を開催していましたが、女性教員の参加は6.6%(1951年)と僅かでした。そこで婦人部は、婦人教員研究協議会を開くようになり、「教員だけでなく、母親とともに運動すべき」という意見が出てきます。そこから運動は「母と女教師の会」に収斂していきます。
これは「女性=母親」という狭い価値観の枠の中に、女性教員を押し込めてしまうという問題はありましたが、(組合内でさえ)今よりはるかに男尊女卑の風潮の強かった時代の運動としては最適解の1つだったのかもしれません。当時の女性教員は、社会と戦う前に、組合内部の男性優位の空気とも戦わなければならなかったのです。
そんな中、地域の母親たちとの連帯を作り出した、高知県幡多郡の女性教師 山中節の実践が民主主義のお手本になります。彼女は地域の一人一人の母親たちに働きかけ、4年以上をかけて「母の日の集い」を組織しました。
ある母親が「4月には教科書代がたまらんでねえ」と発した一言をきっかけに「母の日の集い」をもちかけ、「農業が忙しい」「夫と姑の許可は絶対出ない」と渋る母親たちを説得して回りました。そしていざ集まると母親たちは、日ごろ胸の中に押し込めていたものを一気に吐き出します。昔からの慣習に抑圧されていた当時の女性たちが、本音を吐き出せる場を作った山中は、人々から大きな信頼を得ます。
その後、母親たちは署名運動に取り組み、「教科書無償配布」を勝ち取ります。1人の女性教員の実践が、母親と女性教員の広範な連帯を生み出したのです。
当時の農村部で、進学する人は多くありません。特に女性の場合、「女に学問はいらない」という空気の中、「進学したい」と言えない人もたくさんいました。彼女たちも心の底では、同じ境遇で抑圧されている母親たちと集まり、学び合う日を待ち望んでいたのかもしれません。
社会を変えるには、政治に働きかけて「法律を変えること」と同時に、広範な人々と連帯して「大勢の意識を変えること」が重要です。こうした草の根活動の積み重ねこそが民主主義の基本であると改めて気づかされます。まさに「地方自治は民主主義の学校」という事例です。
教員の労働環境=子どもの教育環境
当時、法定通りに休暇が取れないことは教員に限ったことではありませんでした。「法よりも空気や慣習が重視される」というのは、日本のお家芸ですね。
【余談】欧州は日本と文化が違うので「法が重視されている」と思われがちですが、そんなことはありません。被支配者側の人々が声を上げ、権利を勝ち取ってきた歴史の積み重ねによるものです。今もフランスなどでは、しょっちゅうデモやストが行われています。「欧州だから法が守られる」のではなく、欧州の労働者は黙っていないから、使用者も「法を守らざるを得ない」のです。
そもそも日本では、1986年に男女雇用機会均等法が制定されるまで、「女性は結婚・出産を機に仕事を辞めるもの」という前提で雇用することが認められていました。(この不十分な法ですら、国際社会の批判を受けて渋々制定したものです)
そんな中、女性教員が産休取得を主張することに対して「ずるい」「わがまま」という批判が沸き起こります。もっとも強い批判を寄せたのは当の母親たちでした。「私たちは休めないのに、先生はずるい」ということです。
これに対し「母と女教師の会」は、〈母性保護の重要性〉と〈多人数学級の解消〉を訴え、産休代替教員が配置されることによって、子どもたちにとって適切な教育環境が確保されることを、粘り強く訴えていきます。
「ずるい」という感情的な批判に対して感情的に反発するのではなく、本当に解決すべき問題は「封建制の残滓」「家父長制的価値観」であることを伝え、女性同士の対立にならないよう運動を進めます。
これは、現在の教員の労働問題解決のヒントにもなります。「私はこんなに苦しいのに、あの人はずるい」と教員同士が足を引っ張り合うのではなく、本当に解決すべき問題について学び合い、協力して労働環境を改善していくことが、子どもたちの教育環境を整えることにつながっていくはずです。
教師が声をあげる意味
高度経済成長期以降、高学歴ホワイトカラーの仕事において男女差別が明確になります。高学歴女性は大企業で男性の補助的業務に就き、結婚と同時に退職するのが規定路線となっていきました。
政治もこの動きを税制面から後押しし、女性を「主婦化」していきます。「103万円の壁」「130万円の壁」という矛盾も、こうした過去の遺物です。
すると男性労働力は民間企業に流出し、不足した教員職に高学歴女性が流入してきました。そして1969年度に小学校の女性教員率が5割を超えて以降、結婚・出産後も継続就労する人が増えていきます。当然、産休を取得する人も増えていきました。
権利を行使する時、「みんながそうしているから」という空気は大きな後押しになります。権利として法的に認められているものでも、「みんながやっていないこと」はなかなか広まりません。しかし、まず誰かがファーストペンギンとなり、それに続く人が増えていかなければ、「みんながそうしている状態」は永遠にやってきません。
どんな権利も、初期の頃に要求した人たちは多くの嫌がらせを受けたはずです。そうしたイジメに負けず、先達がつないでくれた権利の尊さを忘れないようにしたいものです。
そして産休代替教員制度を教師が勝ち取り、権利を行使する人が増えてきたことで(最初は「先生だけずるい」と言われたとしても)、その影響が他の職業へも波及して、徐々に産休取得が当然の権利になっていきました。まさにこれが「教師が声をあげる意味」ではないでしょうか?
教師は声をあげやすい?
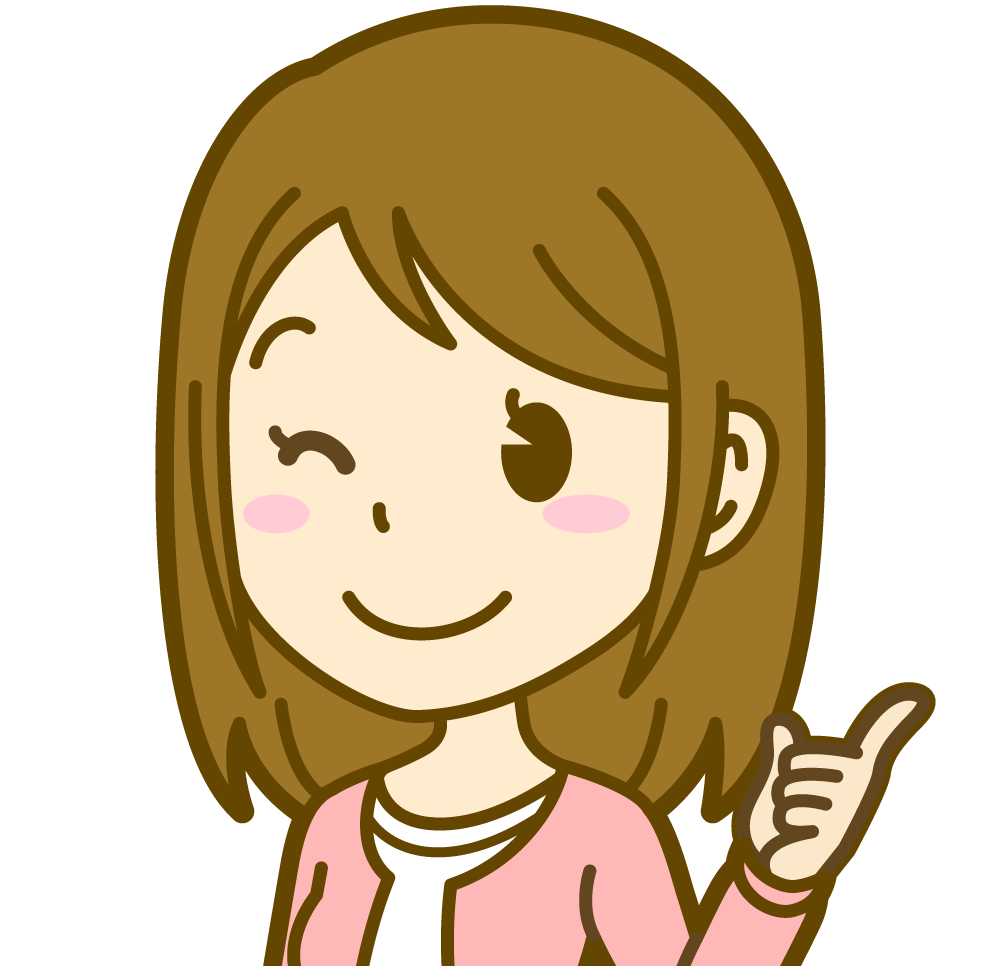
実は、教職員組合には「声をあげやすい理由」があります。
①企業別組合ではない。
②男女ともにたくさんいる。
③比較的男女の不平等が少ない。
などです。
企業別組合ではない
日本の労働組合は『企業別』が基本ですが、世界では『産業別』が基本です。企業別組合だと、労働者の力が弱められてしまうからです。
例えば、A、Bという2つの運送会社があるとします。AとBは値下げ競争をします。企業別組合の労働者は、自社が競争に敗れて職を失うと困るので、賃上げなどを強く要求しにくい構造があります。
一方欧州など、産業別組合の場合はA社の社員もB社の社員も、同一労働同一賃金です。同じ産業内の労働者同士で団結し、労働者の権利を認めさせています。仮に自社が倒産しても、別会社に再就職すれば同じ条件で働けます。だから使用者に対し、従属的にならずにすむのです。
さて、教員の場合はどうでしょう?
隣の学校と競争する必要はありません。もちろん、「よりよい授業をしたい」と思うことは大事ですが、それは子どもたちのためであり、隣の学校に勝つためではありません。「校長への忠誠心が高い教員の給料が高い」なんてこともありません。(最近は人事評価で給料に差をつけ始めました。これからは忠誠心の高い人の給料が高くなるかもしれません。全群教はこの制度に反対し続けています)
群馬の公立小・中・特支学校の教職員ははみんな、「同じ業種に携わる労働者」として全群教に入れます(高校にお勤めの方は群馬高教組へ)。つまり形態としては「産業別組合」で、交渉相手は教育委員会や校長です。だから、おかしいことに「おかしい」と声をあげやすいのです。
男女ともにたくさんいる
先生は日本中にたくさんいます。しかも、男女ともにです。たくさんいる先生たちが連帯して、おかしいことに「おかしい」と声をあげれば、社会を変える大きな力になります。そのいい例が産休代替教員制度の獲得です。
そして先生は子どもたちにとって、親の次に身近な大人です。権利を大切にし、声をあげる先生たちの姿を見て育った子どもは、権利を大切にし、声をあげる大人になっていくでしょう。
だからこそ政府は教職員組合を嫌悪しました。1954年には「教育二法」を制定し、教員の政治活動を制限。1956年には教育委員会を「公選制」から「任命制」にし、勤務評定を強行します。当時の組合員の先生たちは、激しくこれらの弾圧と戦いました。
今も、選挙前になると「教員は政治活動してはいけない」という通知が来ます(こんな脅迫めいた通知を出して萎縮させようとすること自体、憲法違反の疑いがあります)。本当は『教員という地位を利用して政治活動してはいけない』というだけなのですが、あんな通知が出たら「よく分からないから、何も言わないようにしよう」となってしまいますよね。萎縮して、声をあげない教職員が増えることで、政治家が教育に口出ししやすくなります。
組合に加入する人が減り、声をあげる人が少なくなった結果、学校には息苦しさだけが残りました。
大人が声をあげないのだから、声をあげる子どもも育ちません。ブラック労働で疲弊し、声もあげずに使い潰される若者が増えた要因の一つは、教師の萎縮にあるのかもしれません。
比較的男女の不平等が少ない
教員という職業も(特に中学校では)男性優位であることは否めませんが、他の職種に比べれば男女間の不平等は比較的少ないと言えます。そして女性の割合も多いので、団結して声をあげることができれば、女性の権利を勝ち取れるチャンスが多い職業でもあります。実際、産休も育休も教職員組合(特に女性部)の運動で勝ち取り、それが他の職業に波及していった歴史があります。
しかし比較的男女間の不平等が少ないとはいえ、学校でも「子育ては女性の仕事」という空気はあります。子育て中の女性には、「配慮してあげている」と勘違いしている人もいまだにいます。(例えば、「あなたは子育て中だから、部活は副顧問にしてあげている」というような感覚。部活顧問をもたせた時点で時間外労働が100%発生するので、すでに違法状態です)
誰もが定時で帰れて、休みたいときに休める労働環境(=法律が守られる労働環境)を作れば、働きながら子育てすることは十分可能です。「働きながら子育てできる労働環境を作れ」という点で一致できれば、女性が働きやすい、本当の男女平等を求める運動にしていけるのではないでしょうか?
そして「女性が働きやすい職場」は、実は「男性も働きやすい職場」です。まず教師が声をあげ、本当の男女平等を実現できれば、他の職業、そして日本社会全体にも波及していくはずです。
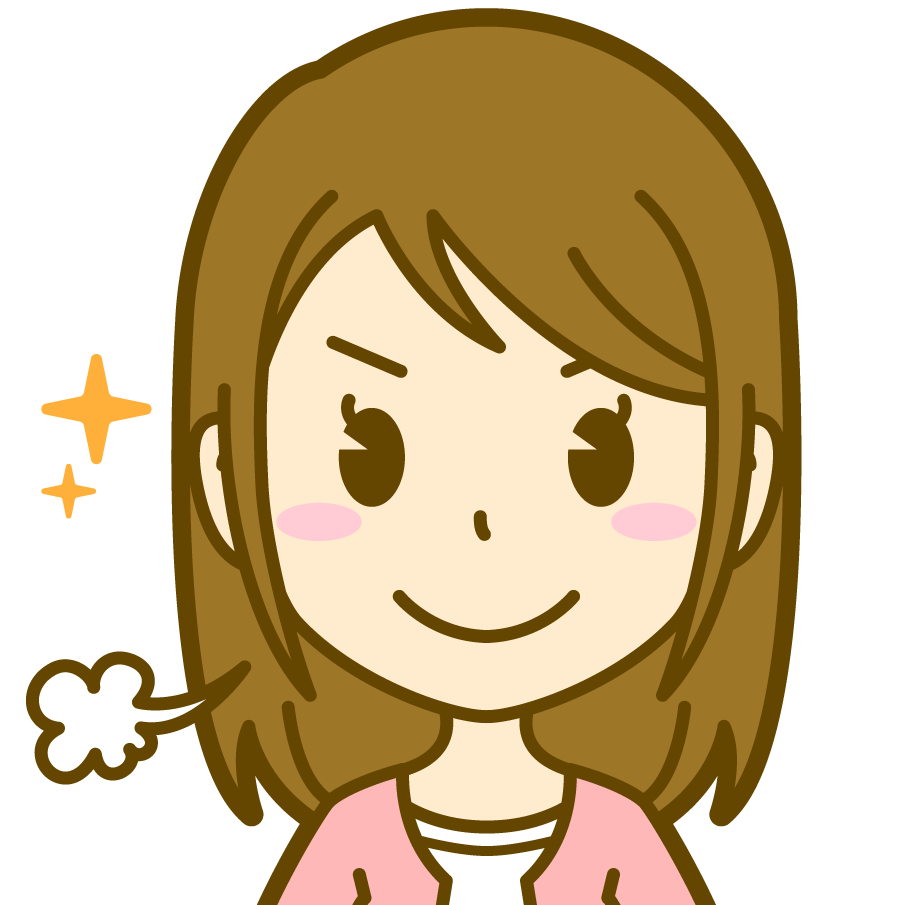
実は、私たちには「声をあげやすい条件」がそろっています。問題は過度な萎縮です。法令を知り、団結すれば、恐れる必要はありません。教職員こそ声をあげ、自分のため、子どもたちのため、そして未来のために社会を変える礎となるべきではないでしょうか?
母親運動の課題
先述した通り、産休代替教員制度を勝ち取るための運動として作り出した「女性教師と母親たち」という連帯は、最適解の1つだったかもしれません。しかし、課題も残しました。
「教育の真諦(しんたい)は母性愛にあり、母親である女性教員こそが教育に適している」という論理は、現在のジェンダー平等の観点からは肯定できません。
この理屈だと、女性教員の存在意義をその教育的専門性よりも「主婦性」や「母性」に求めることになってしまいます。子どもを生んでいない女性教員の否定にもつながり、本質的な男女平等の実現に至る道とは言えないでしょう。
とはいえ、時代とともに社会全体の価値観も変わっていきます。運動の手法も、絶対的に正しい解があるわけではありません。その時代ごとに、みんなで問題意識を共有し、率直に議論していくことが大切です。
育児休業法制定運動方針化までの苦難
日教組で育児休業制度の要求が出てくるのは1963年の定期大会ですが、時期尚早として運動方針化は否決されます。「育休なんて虫が良すぎる。子どもを産んだら辞めたいと思うのが普通の女だ」などという意見も出たようです。
時代が違うとはいえ、現実に苦しんでいる人の訴えを「時期尚早」と切り捨てたり、主観的な「普通の女」像を押し付けたりする態度に憤りを覚えます。
組合内でも、育休制度への賛成・反対は分かれます。
賛成派は「親族に頼めない場合は退職せざるをえない」という現実的な理由。
反対派は「子どもには集団保育が必要。育休は女性を家庭に縛り付けることになるから、保育所増設の方が大事」というイデオロギー的な理由です。(かなり乱暴な分け方をしていることをご承知おきください)
反対派の理由も、論理としては正しいのかもしれませんが、今まさに苦しんでいる人に対して「この論理が正しいのだから、あなたは犠牲になってください」という姿勢には疑問が残ります。
1965年、日教組婦人部は『育児休暇は是か非か可能か』という資料を作成し、育児休業制度の運動方針化を討議します。そして激しい反対を乗り越え、「集団保育か家庭保育かという育児論ではなく、婦人の労働権確立と熟練した婦人教師の退職防止のため」に、育児休暇制度を要求していく方針を固めました。
一方、男性も育休取得の対象とすべきという議論は起こらず、「育児責任を女性のみに押し付けるものである」と批判した人はごく僅かでした。それを思うと、今の状況は(まだまだ不十分とはいえ)隔世の感があります。
育児休業制度の提案から法成立へ
1966年、日教組が育児休業法制定を運動方針に据えた後、1967年に社会党提案として「女子教育職員の育児休業法案」が提案されます。これに文部省・労働省・厚生省が反対。さらに経団連が「民間企業に波及することを懸念」して反対します。
しかし、日教組婦人部は粘り強く運動を続けました。その原動力は国際的な動向に裏打ちされた「本来ならば労働組合の要求や、議員立法などを待たずに政府が実施すべき」という想いです。女性の「育児休暇」は国際機関から各国政府に勧告されていました。
ここに大きな学びがあります。「国際的な常識」とされる人権感覚は、「日本政財界の常識」ではワガママと捉えられ、黙っていれば私たちの人権が蹂躙され続けます。当時の男性優位の組合の中で、声をあげ、行動し続けた婦人部の組合員の方たちの苦労は計り知れません。
そして、1975年に公務員を対象とした「女子教育職員等育児休業法」が制定されました。
法制化に当たり与党自民党は、日教組婦人部が要求した『女性の労働権確立』ではなく、『教師・看護師・保育士の人材不足の解消』を目的とします。さらに『子どもは母親が育てるべき』という家父長制イデオロギーも挿入しました(統一協会も関係していたのでしょうか?)。これは女性の「主婦化」を国の政策として押し進めることにもつながっていきます。
これからの課題
1991年、すべての労働者を対象とした育児休業法が成立し、男性も育休を取得できるようになりました。その後、度重なる法改正を経て、制度的には徐々に整ってきました。しかし、なかなか日本の男性の育休取得率は伸びていきません。なぜでしょう?
ちなみにノルウェーでは男性の4分の3が育休を取得します。しかしノルウェーも権利が自然に降ってきたわけではなく、人々が戦って勝ち取ってきたのです。三井マリ子著『髭のノラ』を読むとよく分かります。日本は50年遅れています。
制度はあっても、取れる環境がないからですよね。
これは育休だけでなく、育児短時間勤務や部分休業といった制度も同様です。むしろ後者の方が浸透していない分、苦しい思いを吐露できずに悩んでいる人がいます。そうした権利を行使する人に対し、とても時間内に終わらない量の仕事を振ったり、嫌味を言ったりする管理職も存在します。そしてやはり、嫌な思いをさせられているのは圧倒的に女性である場合が多いのです。
私たちはこれから、どうすべきなのでしょう?
周りに迷惑をかけないために、権利行使を諦め、口をつぐむべきなのでしょうか?
いいえ
勇気を出して権利を行使する人がいなければ、権利はますます行使しにくくなります。力を合わせて嫌がらせと戦わなければ、ハラスメントが正当化され、次の世代に苦しみを引き継いでしまいます。
現在は、産休に関してのハラスメントは(ゼロではありませんが)なくなってきました。歴史を学ぶと、「制度はあっても使えない」という実態を変えるために、声をあげ続けてくれた先達のおかげだと分かります。
次は、今を生きる私たちが声をあげる番です。50年後の職員室では「昔はパワハラなんてものがあったらしいよ。信じられないね!」という会話がされるようにしていきたいものです。
「自分一人が声をあげても変わらない」と思うかもしれません。それはその通りです。当局との交渉でも、理不尽な屁理屈で押し通されることも少なくありません。
確かに声をあげても、すぐに社会を変えることはできません。でも、自分が「社会によって変えられる」ことは防げます。長い物に巻かれない自分になることができます。組合に入ることで一番変わるのは自分自身の生き方なのです。
あなたがすることのほとんどは無意味であるが、それでもしなくてはならない。それをするのは、世界を変えるためではなく、世界によって自分が変えられないようにするためである。
マハトマ・ガンディー


