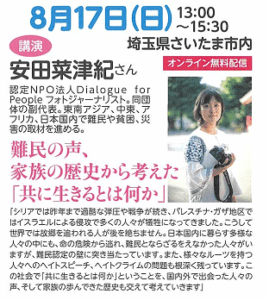美術室・技術室にもエアコン設置へ
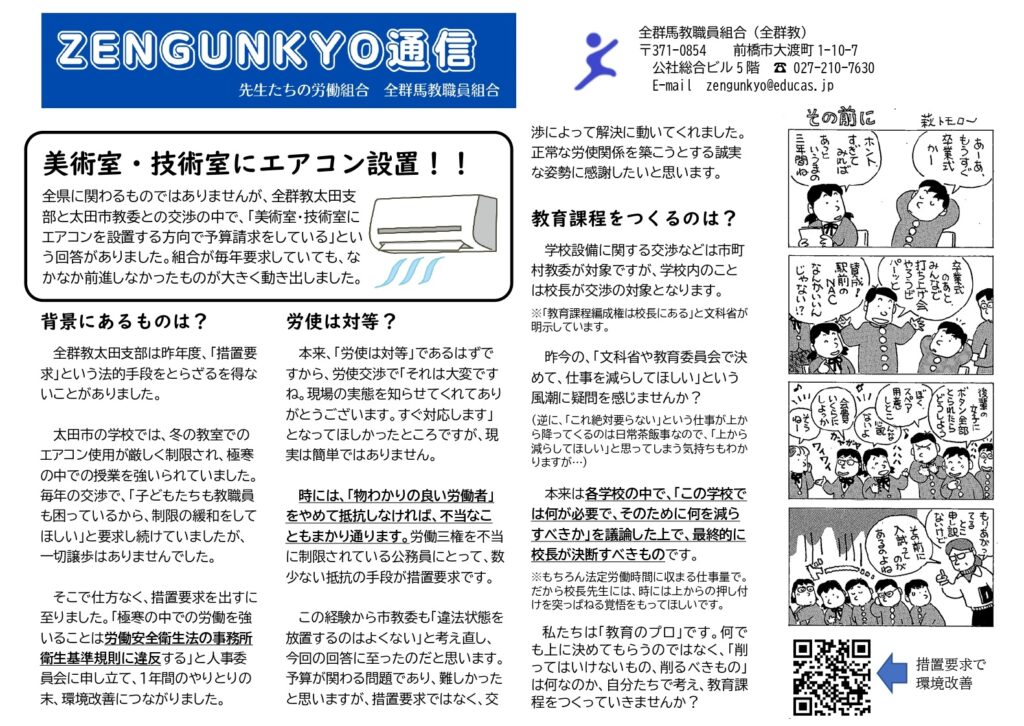
美術室・技術室にエアコン設置
これは非常に大きな成果です。全群教の長年の要求と、措置要求による抵抗の結果です。
「夏、暑すぎて授業にならないからエアコンを設置してほしい」
「冬、寒すぎるからエアコンの設定温度を上げてほしい」
現場の生の声を届けて、そうお願いすれば、「なるほど、そうなんですね。では対応します」となると思いますよね?
しかし労使交渉では、そんなに簡単にことは進みません。特に公務労働の場合、予算が決まっているので教育委員会が何かをするためには財務当局に予算要求することになります。そんなことをするよりも「問題はない」と結論づけ、現場を黙らせる方が楽です。
しかし全群教が「冬、寒すぎる環境で働かせるのは違法である」と、様々な根拠(法的根拠や実際の測定値等)を集めて人事委員会に措置要求を出し、1年かけて「おかしい」とやりとりを続けた結果、冬のエアコン設定温度を上げられるようになりました。
そして今年度の交渉では「予算要求しているので、それが通れば美術室・技術室にエアコンを設置する」という回答を得ることができました。私たちの措置要求によって、教委も「違法状態を放置するのはよくない」と、考えを改めてくれたのだと思います。声をあげること、そして時には抵抗することの大切さを再認識しました。
それ以外の成果
迷惑電話対策として、通話録音を告知するアナウンス
計画的に電話の交換を進めていくという回答を得ました。まだ数校なので、設置のペースを上げていく要求が必要です。
電話で、とんでもなく理不尽なことを言おうとしている人も、「この電話は録音されています」というアナウンスでクールダウンします。学校は保護者からの批判や相談をきちんと聞くべきですが、理不尽な要求にまで対応しようとして、心を病んでしまう場合もあります。今まで軽視されてきた、教職員の人権を守るための対応が必要です。
部活顧問強制をなくす
これは毎年確認し、「顧問の強要がないよう指導する」という回答を得ています。しかし実態は同調圧力による強要があるので、これをなくすためには組合員を増やしていく必要があります。
施設管理責任は管理職にある
これも毎年確認し、「学校管理規則に則って管理するよう、管理職を指導していく」という回答を得ています。以前は勤務時間終了後、日直に施錠させることが普通でしたが、そういう学校は減っているはずです。日直を廃止した学校もあります。実は、全群教の要求の成果です。
修学旅行等の割り振りは、その週内に取らせる
週の労働時間は38時間45分です。修学旅行などの超過労働分は、その週内に休ませなければ「疲れを取る」という本来の意味をなしません。それを知らずに「夏休みにとってください」などと平気で言う管理職もいるため、この要求も毎年確認しています。
職務上の賠償責任は国賠法で対応
県教委交渉で勝ち取った合意を市レベルでも確認しました。簡単に言うと、プールの水道代を賠償する場合などは、市が責任を持つということです。
詳細はPDFファイルでご確認ください。
合意に実効性をもたせるには
しかし、いくら組合と教委の間で適法かつ建設的な合意をしても、その合意に実効性をもたせるためには「どの学校にも組合員がいる」という状況を作る必要があります。組合が介在せずに個人で交渉すると、労働者は不利な条件で合意させられてしまうことが往々にしてあります。
例えば教委と組合で「顧問強制はできない」と合意していますが、明確に断らない限り、「強制はしていない」という言い訳が成り立ちます。そして現状では個人で断った場合、圧力をかけられ、引き受けさせられることが多いはずです。
また、プールの水道代を「あなたのミスなのだから、穏便に済ませるために払ってほしい」と言われて払ってしまえば、「合意して自己負担した」ことになります。本来払うべきではありませんが、「自分がミスをした」という負い目から、払ってしまうケースも少なくありません。払った後に「やっぱり納得がいかない」と考え直し、決定をひっくり返すためには裁判が必要になるでしょう。それよりも、最初から組合を通して交渉し「国賠法で対応する事例ですよね」と、もめる前に解決した方がシンプルでスマートです。そして組合に加入する権利が法律で保障されているのは、そうやって解決することを想定しているからです。
組合と教委で合意しても、それが具体化されていない事例はいくらでもあります(例えば、修学旅行の振替を夏休みに取らせるなど)。合意に実効性をもたせるには、すべての学校で管理職と話し合い、合意形成をしていく必要があります。つまり、「組合員を増やす」ことが絶対に必要なのです。
「美術室・技術室にエアコンを入れることに賛成」という方は、ぜひ組合に入ってください。「矢面に立つことはできない」という方も、後ろから支えてほしいと思います。役員は、「支えてくれる組合員がいる」と思うことで頑張れます。